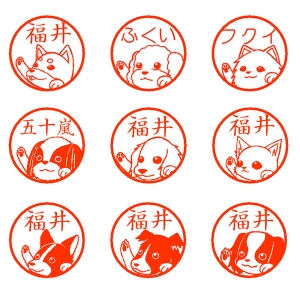1.椎間板ヘルニアの術後のリハビリテーション
椎間板ヘルニアは犬で最も多い神経疾患であり、症例の重症度によっては外科手術が選択される。一般的に、手術の適応となる症例は重度の麻痺であることが多く、リハビリテーションの主な目的は起立および歩行機能の回復である。その目的を達成するためには、術後の早期から適確なリハビリテーションを行う必要がある。
椎間板ヘルニアの症例で手術を行った動物においては、もはや圧迫物質が脊柱管内に存在していないため、術創さえ癒えれば比較的に積極的なリハビリテーションを展開することができる。すなわち、ケージレストのみを強いるのではなく、術創の治癒を悪化させないように保護しながら行えば、術後早期からのリハビリテーションが実施可能である。近年、深部痛覚を消失した症例であっても、約60%以上の症例において歩行が可能となることが報告されている。この成績の向上は、リハビリテーションの発展の成果と言っても過言ではなく、その重要性は認識されている。しかし、麻痺が重度な動物では、起立および歩行機能が回復するまでに長い期間を要するので、長期的な視野に立った目標設定が必要となる。ここでは、いずれの施設においても行うことのできる方法を紹介する。
手術直後のリハビリテーション
手術の当日から3日以内までは、脊柱に負担の大きいリハビリテーションは控えた方が賢明である。術創の疼痛管理の目的で鎮痛剤を投与し、必要であれば手術部位の周囲を15分程度冷却する。廃用性筋萎縮の予防またはその速度を緩徐にするために、麻痺肢のマッサージを行う(図10)。関節が拘縮しないように、屈伸運動(図11)または自転車漕ぎ運動を行う。完全麻痺の症例では、引っ込め反射を誘発させることで、神経と筋肉の連動性を高めることができる(図12)。これらのリハビリテーションは横臥位で行うか、手で体重を支えて起立させるなどして、全ての時間を脊柱に負担のかからないようにして行うのが望ましい。リハビリテーションの頻度は1日に2~3回で、残りの時間はケージレストによる運動制限を行う。
自力起立を促すリハビリテーション
術後2~3日以上経過したら、補助起立を開始して起立能力の回復に努める。術創の疼痛管理が必要であれば、手術部位周囲の温熱療法やTENSを適用する。麻痺肢の筋萎縮を改善する目的でマッサージを行う(図10)。麻痺肢の関節可動域(ROM)の維持および改善の目的で、屈伸運動(図11)や他動的関節可動域訓練(PROM)も継続して行う。神経機能の回復を目的として、引っ込め反射の誘発も継続的に行う(図12)。起立位を憶えさせるため、または起立能力を回復させる目的で、補助起立による起立訓練を1回に5分程度から開始する(図13)。起立訓練を行う時には、手で十分に体重を支え、可能であれば麻痺肢に体重がかかるように補助する力を緩めて自力での起立を試みる。約1分以上の自力起立が可能となるまでは歩行訓練を控えた方が良い。自力で起立できない時期から無理矢理に歩行訓練を開始すると、健常肢のみで歩行することを覚えてしまい麻痺肢での歩行を促すことができないため、早すぎる歩行訓練は推奨しない。これらのリハビリテーションは、1日に2~3回の頻度で行う。
歩行能力を回復させるためのリハビリテーション
自力での起立が比較的に長い時間できるようになったら、能力に応じて歩行訓練を開始する。麻痺肢のマッサージ(図10)やPROMを行ってから歩行訓練を行うとより効果的である。この時期からは、NMES(図3)、LLLT(図6)、超音波療法などの物理療法を適用することが可能である。歩行訓練は、手やタオルで体重を支えながら一歩ずつ確実に行う(図14)。長い距離の補助歩行が可能となったら、スリング(吊り帯)を用いて歩行訓練を行い、できる限り長い時間を自力で歩行させる。スリングでの長時間の歩行訓練は、治療を行う者にとって負担となることが多い。長時間の歩行訓練を行うために、補助歩行用車椅子を用いたカートセラピーを適用すると効果的である(図15)。水中トレッドミルなどを用いたハイドロセラピーは、浮力により脊柱への負担が軽微な状況下で補助歩行を行うことができるので、歩行のパターン化を達成するのに有効である(図16)。このような補助を必要とせずに、自力での歩行が可能となったら、1日に2~3回の短時間の散歩を開始する。
協調性のある歩行を獲得するためのリハビリテーション
長時間の歩行を行うことが可能となっても、ナックリングや肢を引きずるといった障害が残存することがある。このような状態を完全に改善させるために、ダンシング、座り立ち運動、スイスボール運動(図17)、バランスボード運動といったリハビリテーションが効果的である。機能回復期には、トレッドミル(図16)、ハイドロセラピー、ジグザグ歩行、円周歩行、カバレッティーレール、ジョギングといった自発的な運動療法を取り入れて完全回復を目指す。切り返しを伴う運動や、段差およびジャンプは、椎間板ヘルニアの再発防止という観点からも避けるべきである。これらの運動療法は急がずに、適度にかつ計画的に行うことが重要である。
2.大腿骨頭切除術後のリハビリテーション
大腿骨頭壊死症、股関節形成不全、外傷性股関節脱臼といった疾患の治療法として、大腿骨頭切除術が選択されることがある。大腿骨頭切除術を行った動物では、術後の再脱臼や再骨折といった合併症が生じないために、比較的に早期から積極的なリハビリテーションを展開することが推奨されている。患肢の不使用や拘縮を防ぐためにも、術後のなるべく早期からの適確なリハビリテーションが必須である。術創の癒合を悪化させないように気を配りながら、手術直後から着肢訓練および起立訓練を積極的に開始し、廃用性筋萎縮の程度を最小限にすることが最初の目標となる。これらのリハビリテーションを行う時には、疼痛が妨げとなることがあるので、厳格なペインコントロールを行うことも重要である。十分な負重をかけた着肢や起立が可能となったら歩行訓練を開始する。この時期には、一般的に強度の高い運動療法を安全に行うことができる。ここでは、いずれの施設においても行うことのできる方法を中心に紹介する。
着肢および起立を目的としたリハビリテーション
大腿骨頭切除術後は、廃用性筋萎縮と拘縮を予防または最小限にするために、手術直後から積極的に着肢および起立訓練を開始する。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を投与して疼痛の緩和を試みることにより、これらの訓練を早期から確実に実施することができる。TENSや寒冷療法も、この時期の疼痛緩和や術後の腫脹を抑制するのに有効である。着肢および起立訓練を行う前に、マッサージや屈伸運動を行うとより効果的である(図18)。股関節の線維性関節包の形成を障害しないように、手術直後には股関節領域の屈伸運動やストレッチを避けるべきである。
最初は手で体重を支えて、患肢に過剰な負荷がかからないように注意しながら着肢訓練を行う。踏み直り反応(図19)や姿勢性伸筋突進反応(図20)といった姿勢反応を利用することにより、動物が苦なく容易に着肢訓練を行うことができる。これらの着肢訓練は、手術翌日から行うことを推奨する。
着肢時に少しずつ負重がかけられる様になってきたら、徐々に負荷を増やしていき自力での起立を試みる。可能であれば、健常肢を挙げて患肢のみで起立させるなど、より自発的な着肢および負重訓練を行う(図21)。このようなリハビリテーションを1日2~3回行うことで、ほとんどの症例が手術4~14日後までには着肢が可能となる。
歩行能力の回復と筋力強化のためのリハビリテーション
着肢が常時可能となったら、歩行訓練を開始する。NSAIDsの投与を継続することで、歩行訓練を円滑に行うことができる。歩行訓練を行う前に、患肢の温熱療法を10分ほど行うと良い。まず、患肢のマッサージから行い、疼痛が生じない範囲内で股関節の屈伸運動やPROMを行う。続いて、引き紐で後肢に十分な体重をかけながら、短時間のゆっくりとした散歩を行う。最初は、5分程度から開始し、1週間に5分位のペースで距離を伸ばしていく。術後2週間以上が経過したら、股関節のストレッチや座り立ち運動を行い、股関節のROMの改善を図る。患肢への体重負重が十分に行うことが可能で、跛行がほとんど認められなくなったら、NSAIDsの投薬を中止する。機能回復期には、制限下であれば、ジグザグ歩行、円周歩行、カバレッティーレール、ジョギングといった、ほとんどの自発的な運動療法を安全に行うことができる。水中トレッドミルや自由遊泳などのハイドロセラピーは、大腿骨頭切除術後のリハビリテーションに特に有効である。これらの運動療法の最後には、寒冷療法を行ってクールダウンをする。この時期には、超音波療法、電気刺激療法(TENS、NMES)、LLLTといった物理療法の併用も効果的である。平均的に手術1ヵ月後までには、ほぼ正常な肢の運びと体重負重、そして速歩を行うことができる。
さいごに
動物医療におけるリハビリテーションの最近の考え方について4回に渡り述べた。近年では、わが国においても多くの施設でリハビリテーションが導入され始めており、急速に普及しつつある。また、一部の施設では、欧米の動物理学療法士の認定を受けた者が治療を行っており、世界基準のリハビリテーションが展開され始めている。リハビリテーションは、整形外科疾患や神経疾患の動物が機能回復する上で大変重要であることに疑いはない。しかし、リハビリテーションはあくまでも適切な内科療法や外科手術を行った上での補助療法であることも常に頭に入れて治療を行うべきである。また、リハビリテーションを行う者は、それぞれの療法の目的、正しい方法、効果、強度を理解し、科学的根拠に基づいて行うことが機能回復にとってきわめて重要である。これは、治療による二次的損傷や合併症を防ぐということにも役立つ。リハビリテーションを行う際には、医療スタッフ間の情報共有と家族への教育も重要な位置を占める。これらの点を十分に考慮して、リハビリテーションを展開していくことが理想的である。本連載が、犬や猫のリハビリテーションを行う時の参考となったら幸いである。
参考文献
- Millis, D., Levine, D., Taylor, R. ed. Canine rehabilitation and Physical Therapy. W B Saunders Co. Philadelphia. U.S.A. 2004.
- Bockstahler, B., Levine, D., Millis, D. Essential Facts of Physiotherapy in dogs and cats. -Rehabilitation and Pain Management -. BE Vet Verlag. Babenhausen. Germany. 2004.
- Gross, D.M. Canine Physical therapy. Orthopedic physical therapy. Wizard of Pow, East Lyme. U.S.A. 2002.
- Fossum, T.W. ed. Small Animal Surgery. 3rd. ed. Mosby. Philadelphia. U.S.A. 2007.
- Kazuya Edamura. Rehabilitation in dogs and cats with spinal diseases. Jpn. J. Vet. Aneth. Surg. 37(3): 49-60. 2007.
- 枝村一弥. 小動物のリハビリテーションの現状と将来-科学的根拠に基づいたリハビリの実際-. 獣医畜産新報. 618(10):807-814. 2008.
- 枝村一弥. リハビリテーションの基本と考え方. In: 勤務獣医師のための臨床テクニック3. 石田卓夫監修. チクサン出版. 東京. 2009.
カテゴリから探す